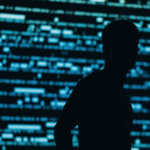【柔軟性 vs. 技術】サプライヤーに安さを求めるリスクの理解

みなさんこんにちは、applemint 代表の佐藤 (@slamdunk772) です✌️
今日は、「サプライヤーに安くて良いものを求めるのは一見良さそうに見えるけれど、長期的にはリスクになる可能性もある」という話をしたいと思います。
これは最近、実際にあった事例です。
ちなみに広告代理店との取引でも、広告代理店を何でもやってくれる“便利屋”のように考え、その結果、クライアントが離れられなくなるケースがあります。
これも本質的には似たような話だと思っています。
この二つの共通点は、過度な依存性を作ってしまうってことです。
台湾で多くの人や会社を見ていて思うのは、最初は依存しているつもりがなくても、結果的に依存してしまうパターンが意外と多いということです。
ただ、依存性を作り出す側も注意しないと長期的には負けます。
今日は、安さの沼にハマった企業の事例と、便利屋となったサプライヤー(サービス提供者)が長期的には負けた事例をご紹介します。
僕らとの契約を打ち切りたいけど何もできないA社

先日のある日曜日。出張で溜まった仕事を家で片付けていると、あるお客さんの社長からメッセージが届きました。
このお客さんはそこそこの規模があり、しかも社長は日本在住なので普段、僕に直接メッセージしてくることはほとんどありません(特別に仲がいいわけでもない😅)。
「これはきっと悪いニュースだな…」と覚悟しつつ開いてみると、メッセージの内容は…
「少し話す時間もらえますか?」
おいっ👊👊って感じでしたね。
こういう時って、いいニュースなわけがないですよね?😅
作業の手を止めて返信すると、すぐに「今から話せます?」と来たので、「あーこれは相当まずいな」と思い、すぐに電話しました。
案の定、デジタル広告全体のパフォーマンスが悪く、撤退を検討しているみたいな内容でした。
その場では短期的なアドバイスをして事態は収拾しましたが、次の日の月曜日には台湾人の担当者間で広告停止の話が出たそうです。
さらに担当者は、「手数料を節約するために広告を内製化したいので、やり方を教えてもらえませんか?」と、うちの担当者に打診してきたらしいのです…
そんな都合のいい話あるか!👊👊みたいな感じでお断りしました😅
残念ながら、このお客さんにはもう内製化以外にコスト削減の手段が残っていません…
ただ、内製化って難しいんですよね…
内製化で難しいのはインセンティブの設計です。
経営陣からすると、内製化はコストを下げられて最高ですけど、それがすぐにスタッフの給与に反映されるわけではないので、スタッフから見れば仕事が増えて給与一緒なのでやる気が上がらないんですよね…
これはapplemintでも同じで、僕がいろいろ実験していた社内動画制作も、インセンティブがないため僕とインターン以外は動かず、ずっと止まっています😅
おまけに台湾だとスタッフが辞めやすいので、内製化するにもバックアップメンバーがいないときついです。
話を戻すと、結局このお客さんには、撤退以外の選択肢はありません。
僕らの手数料がリーズナブルな上に、今まで “便利屋”的に何でもやってしまっていたからです。
本来ならお金をもらっていいことも、長年の付き合いもあり、お手伝いを続けてきました。
その結果、僕らみたいにリーズナブルで、柔軟性がある代理店っていないので、他の選択肢がないんですよね…
こんな感じで相場よりかなり安い金額を設定して、なんでも任せると後々やめづらくなるというリスクは理解しておいたほうがいいでしょう。
便利屋から抜け出せない顧客

ここで”便利屋”について少し補足します。
広告代理店をしていると、本当に様々な企業や人に出会います。
その中で「あ、この人ちょっと危ないな…」と思うのは、広告代理店に何でもかんでも仕事を丸投げしてくるケースです。
中には、自分たちの会社の目標値やKPIの設定まで任せてくる人もいます…(おいおい😔)
広告代理店の立場から見ると、こういう会社はカモです。
お客さんから見ても、柔軟に対応してくれる広告代理店は最高です。
広告代理店に仕事を振っておけば自分は楽をして、それなりの給与を得られますからね。
こうして歪な win-win が出来ます。
結果として、ズルズルと関係が続き、新任者が前任者の“丸投げっぷり”を見て驚き、契約を打ち切るってケースは実際によくあります。
もし会社のスタッフが誰かに過度に依存しているようなら、それは要注意だと個人的には思っています。
最近何かと話題の TSMC vs. UMC の話

広告代理店は便利屋になれば、相手を中毒にして依存させることが出来ていいのではないかと思うかもしれません。
でもそうじゃなかったりもするのがビジネスの悩ましいところです。
実は、長期的に見ると、相手の顔色を窺ってスピーディーに柔軟に対応する便利屋よりも、技術革新を絶えず行い、顧客に対して一歩先の解決策を提供する方がいい事例があります。
それが、台湾半導体大手 TSMC と UMC の比較です。
最近2ナノメートルの技術が流出して何かと話題の TSMC ですが、彼らと2000年代初頭までライバルだった UMC の歩みを見ると、実は便利屋のリスクも浮き彫りになります。
あ、TSMC について詳しく知りたい方は、以下の本をご覧ください:
知らない方のために UMC の話をざっくりすると、UMC は TSMC 同様に台湾の国家プロジェクト『工業技術研究院』から生まれた会社です。
- 工業技術研究院
ハイテク産業化を目指した台湾が、ハイテク分野の研究と開発をするために設立した財団法人。
UMC は元々 Intel みたいに半導体完成品を生産する IDM として出発して、その後ファウンドリーになりました。
ちなみに、UMCの創業者・曹興誠(ロバート・ツァオ)は、先日のブログでも触れた『零日攻擊』に多額の出資を行い、中国からの脅威を訴えています。
さて、このUMCですが、当時はTSMCと激しく競い合っており、両社が南部に新工場を建設することになった際には、一方が4,000億台湾ドルの投資を発表すれば、もう一方は5,000億台湾ドルで応じる、みたいなことをしてました😅
また、両社間では人材の移動もちょくちょくあり、例えば TSMC設立当初にCFOを務めていた人物が退職後にUMCへ移籍するなんてこともありました。
しかし、そのTSMCとUMCの間には、次第に大きな差が開いていきます。
UMCは2000年から2010年にかけて売上が伸び悩んだ一方、TSMCは驚異的な成長を続け、現在では両社の売上規模に数倍の差があります。
『TSMC 世界を動かすヒミツ』の中で著者は、TSMCは技術向上と研究開発に長期的に取り組み、「顧客を勝たせて自らも勝つ」という戦略を選んだ一方、UMCは機知に富んだスピード感ある行動や、柔軟な対応・配置戦略を強みとしていたことが、両社の分かれ目になったと述べています。
(そのほか、TSMCは自社で最新技術の開発に成功した一方、UMCはIBMと提携して開発を進めたものの、TSMCから2年遅れてようやく成功し、この遅れが差につながったとも述べられています。)
一見すると、UMCには何の問題もないように見えますよね(少なくとも僕にはそう見えました😅)
しかし著者によれば、スピードと柔軟性のある製品生産は完成品を製造する企業には魅力的でも、ファウンドリーとしては適していないと指摘しています。
残念ながら、半導体業界ではその後、Appleをはじめとするメーカーが独自に設計を行うようになり、徐々に設計から生産まで一貫して担う完成品の需要が減少しました…(Intel の経営悪化はまさにこの影響を受けている)
UMCもファウンドリービジネスへの転換を余儀なくされましたが、その後従来のやり方で顧客と向き合った結果、主導権を握れず、苦戦します。
一方でTSMCは、柔軟性やスピードを重視しつつも、とにかく技術革新をスピーディーに行う事に力をいれ、最先端技術で顧客を勝たせることを一番にしました。
その結果、本来脆い立場になりやすいサプライヤーである TSMC がむしろ主導権を握るような体制を築きました。
この事例から分かるのは、いくらスピードや柔軟性があっても、正しい方向で努力し続け、顧客を勝たせるための技術革新を怠らないことが、長期的な成功には不可欠だということでしょう。
MBA vs. 現実

最後にちょっとおまけで、 MBA vs. 現実という話をします。
うちのスタッフが面白い話をしていたので、ご紹介します。
MBA ではよくリーダーシップやマネージメントのクラスが開かれています。
僕も政治大学の MBA に通っていた時は、よくそんなクラスを取ってました。
ただ、今思うのは、マネージメントは絶対クラスで学べないことです👊👊
例えば、次のような場面に遭遇したら、皆さんはどうしますか?
あなたはサッカーチームの監督で、チーム内ではコーラを飲むことを禁止しています。
ところが、あなたのチームにいる絶対的エースで、圧倒的な結果を出し続け、代わりの効かない世界的スター選手が、あなたの目の前でコーラを飲んだとします。
そのとき、あなたならどう対応しますか?
これは実際にあった出来事で、当時バルセロナの監督だった世界的名将グアルディオラがコーラ禁止令を出していたにもかかわらず、メッシが目の前でコーラを飲んだそうです。
「どれだけ反抗的なの?というか、普通コーラなんて飲まないでしょ!性格悪っ!」と思いましたね😆
このとき監督が取った行動を知りたい方は、ぜひ以下の動画をご覧ください。
なんと、グアルディオラはメッシだけは例外としてOKにしたそうです…😱😱
おそらくMBAの授業でマネジメントを学んだら、「一度例外を認めるとルールが次々と破られるので、メッシにも禁止すべき」という意見が大半を占めるでしょう。
グアルディオラも本心では禁止にしたかったはずですが、理想と現実の間にはなかなか大きな隔たりがあるものですね…
以上、applemint代表の佐藤でした!